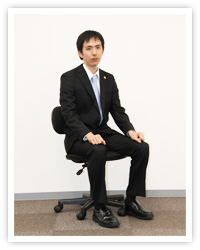毎年有斐閣から重要判例解説という、去年1年間に出た実務上意義の大きい裁判例をまとめた書籍が出版される。弁護士の必読書の1つといえる。
その中から、私が注目したものを一つ紹介する。大阪高裁令和5年12月19日判決(令和5年(ネ)62号)である。
1 事案の概要
Xは、協同組合Yの組合員であり、501万円の出資を行っていた。Xは通常民事再生を申し立てて令和2年1月開始決定を得て、令和3年3月末のYの事業年度末でYを脱退して出資金を払い戻す意思表示をした。YはXに対して約1000万円の貸金債権を有しており、令和3年2月に1000万円の貸金債権の債権届出をするとともに、出資金払戻債務を対当額で相殺する意思表示をしたが、XはYに対し501万円の支払を求めて提訴した。
出資金は、前年9月までに脱退の申込があれば、翌年6月の総代会で払戻金額を確定して総代会終了後に払戻しを行うので、Yの相殺は停止条件不成就の利益を放棄して行われた。
2 判決の要旨
民事再生法92条1項は、再生債権者が相殺によって消滅させることのできる債務の範囲を制限することで、再生債権者の相殺の担保的機能への期待と再生債務者の事業の再建との調整を図ったものである。
同項により再生債権者がすることが許される相殺における受働債権にかかる債務は、再生手続開始当時少なくとも現実化しているものである必要があり、将来の債務など当該時点で発生が未確定な債務は、特段の定めがない限り含まれないと解するのが相当である。
このことは、旧商法上の会社整理で停止条件付債務を内容とする契約が会社の整理開始前に締結された場合であっても条件が整理開始後に成就したときは相殺を禁止していると解されていたこと(最判昭和47年7月13日)にも整合する。
として、Yの相殺の主張を認めず、Xの出資金払戻請求を認容した。
(参考:民事再生法92条1項:再生債権者が再生手続開始当時再生債務者に対して債務を負担する場合において、債権及び債務の双方が第94条第1項に規定する債権届出期間の満了前に相殺に適するようになったときは、再生債権者は、当該債権届出期間内に限り、再生計画の定めるところによらないで相殺することができる。)