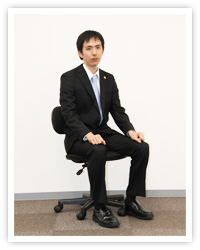日々思ったこと、皆様のお役にたてる情報などを書いていきたいと思います。
ようこそ、弁護士 岩橋 毅彦のブログへ
事業が続けられるかの見極め
1 事業が続けられるかを見極めるポイント
事業再生にたずさわる弁護士のもとには、何とか事業を続けたいが資金繰りが厳しいという代表者の方が毎月何人も相談に来ます。
事業が続けられるかは、事業形態や権利関係によるところもありますが、弁護士が簡単に見極めるポイントとして使っているものをお伝えします。
2 事業に不可欠な経費の支払いができるだけの現金預金があること
たとえば仕入をして売る業種では、仕入代が払えず仕入ができなければ、事業として成り立ちません。
従業員が店に立ってくれなければできない業種で、給料が払えないなら、事業を続けることはできません。
金融機関への返済額は、弁護士が入って調整することもできますが、事業に不可欠な経費の支払いができなければ、事業は続けられません。
そのため、給料や大きな仕入代の支払日に、支払いに必要なキャッシュ(現金預金)が残っている必要があります。
よく資金繰りの相談に行くと、会社の資金繰り表を作るよう言われるのは、入金が後で支払いが先だと、たとえ黒字でも支払いができなくて事業が続けられないケースがあるからです。
3 返済をしなければ黒字にもっていけるか
赤字であっても、現金預金が残っている限りは事業が続けられるといいます。
ただ、弁護士のところに事業再生の相談に来られる会社は、現金預金が少なくなっており、かつ赤字の会社が多いので、赤字が数カ月続くだけで現金預金がなくなりそうなケー
スが多いです。
すると、赤字から黒字になるプランを数カ月で実行しなければなりません。
どこまで黒字になればよいのかというと、最低限は返済を0と仮定した場合の黒字です。
事業を続ける以上、一旦返済を止めることはできても将来的に返済できる見込みがないと、事業を再生したり借金を減額してもらうことはできません。
4 投じられる個人資産や融資も検討
主には2と3が事業を続けられるかの簡単な目安になりますが、補助的には、現金預金以外に、現金化しやすそうな会社又は代表者個人の資産がないか、代表者個人も含めて融
資を受ける余地がないか検討します。
たとえば解約してお金が返ってくる保険、活用できていない車両の売却等で現金が手に入れば、仕入代や人件費に充てられます。
ただ、借りた直後に資金繰りができなくなって倒産すると、計画倒産とか返済する意思がないのに借りたとして詐欺罪に問われる可能性もありますので、融資は慎重に検討しま
しょう。詳細は事業再生に強い弁護士にご相談ください。
性同一性障害特例法の生殖不能要件を違憲とする判決
1 重要判例解説
令和5年度重要判例解説が、令和6年5月20日発行されました。1年分の社会や法律家の実務に大きな影響を与えそうな裁判例をまとめた書籍で、例年4月10日頃までに発行されていたと思うのですが、今年から発行が5月になりました。弁護士実務を続けていくうえで、判例の変更を追いかけるのは必須の研鑽といえます。
私が注目したのは、性同一性障害特例法の生殖不能要件を違憲とする判決(最高裁令和5年10月25日大法廷決定)です。
2 事案の概要
Xは、生物学的には男性だが、女性への性別取扱いの変更を申し立てたが、「生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること」(性同一性障害者の性別の取扱いの
特例に関する法律第3条第1項4号)(以下、「本件規定」という。)に該当しないという理由で、申立てが認められなかった。
Xは、4号が憲法13条に違反するとして争った。
3 決定の要旨
本件規定が必要かつ合理的な制約を課すものとして、憲法13条に適合するか否かは、本件規定の目的のために制約が必要とされる程度と、制約される自由の内容及び性質、具
体的な制約の態様及び程度等を較量して判断されるべきである。
本件規定の目的は、性別変更前の性別の生殖機能により子が生まれることで生ずる親子関係名地に関わる問題による混乱の防止、生物学的な性別に基づく男女の区別に対する急
激な変化を避ける必要等の配慮に基づく。
しかし、性同一性障害を有する者は社会全体から見れば少数である、1万人を超える者が審判を受けて性同一性障害を有する者への理解が広まりつつあること等から、制約の必
要性は低減している。
一方、医学的知見の進展に伴い、治療としては生殖腺除去手術を要しない性同一性障害者に対し、身体への侵襲を受けない自由を放棄して強度な身体的侵襲である生殖腺除去手 術を受けることを甘受するか、又は性自任に従った法定上の性別の取扱いを受けるという重要な法的利益を放棄して性別変更審判を受けることを断念するかという過酷な二者択一を迫るものになった。そのため、本件規定による制約の程度は重大である。
4 意見
最高裁は、平成31年1月23日の決定で、本件規定を憲法違反でないとしており、4年の間にどんな変化があって判断を180度変えたのか疑問に感じる点がある。
しかし、生殖腺の除去は、私見では昔の外国の刑罰を思い起こさせ、この判例がいうように、過酷であると思えるので、この判断は妥当であると考えられる。
遺産分割と破産
1 遺産が残っていれば自己破産でお金にかえなければならない可能性がある
亡くなったお父様の遺産が残っている方が自己破産する場合、遺産はどうなるでしょうか。ここでは、令和6年1月1日にお父様Aが亡くなり、ローンが残っていない自宅の不動産を所有していました。ご存命のお母様をB、破産する方をCとしてみます。
Aの財産は、何もしなければ、Bが2分の1、Cが2分の1ずつ共有していることになります。
Cが自己破産する場合、A名義の不動産の2分の1をお金にかえなければならないのが原則です。
2 破産申立前に遺産分割しても否認権行使の可能性がある
では、Cが自己破産を依頼する前に、Aの遺産を全部Bに相続させるという遺産分割協議をして、B名義で登記した場合はどうでしょうか。
この場合、不動産は形式的にはCの財産ではありません、
しかし、破産の直前に財産を他の人に全部タダであげてしまうのは、財産隠しの一種になり、否認権行使といって裁判所が選んだ破産管財人から取り返されて現金化される可能性もあります。
ただ、これには、遺産分割と単なる贈与を同視すべきではなく、遺産分割協議が民法906条が掲げる事情と無関係に行われ、遺産分割に仮託してされた財産処分であると認めるに足りる特段の事情がある場合にしか無症候否認の対象にならないという裁判例(東京高等裁判所平成27年11月9日判決)もあるところですから、なぜ自分の取り分がなく全部母名義にするのかについて合理的な説明がつくかどうかも重要になります。
3 相続放棄
破産申立てする弁護士としてこの問題を解決するには、Cが相続放棄ができないか検討するでしょう。
相続放棄は一身専属性があり、詐害行為にならないという最高裁判例があるからです。しかし、相続放棄は亡くなったことを知ったときから3ヶ月以内に行わなければならない
のが原則なので、先の例では令和6年4月1日までしか行えない可能性があります。
4 個人再生
破産でなく個人再生の場合も同様の問題が生じますが、個人再生では実際に相続財産を換価するのでなく、清算価値に計上して返済すれば足ります。
つまり、返済額は増えるが、自宅をお金にかえる必要はないということです。そこで、返済能力があるなら、Cが自己破産でなく個人再生を選択することも検討すべきでしょう。
認知症等で判断能力が衰えている方の法的手続
1 認知症等で判断能力が衰えると、法的な手続きが一人でできなくなる
弁護士が相談にのる方には、認知症や脳梗塞等で判断能力が衰えたり、意思表示が十分にできない状態になってしまった方もいらっしゃいます。
法律の世界では、成人した方は、自分で自分の財産や権利を守ることができることを想定していますが、病気や高齢によって判断能力が衰えた場合に放っておくと、悪徳商法に引っ
かかって財産を失うなどの問題が生じかねません。
そこで、判断能力が衰えた場合は、その程度によって、家庭裁判所に申請して、成年後見人、保佐人、補助人という判断を助ける人を選任してもらう手続きがあります。
成年後見人、保佐人、補助人が選任された場合、複雑な法的手続きは一人ではできなくなり、成年後見人等が代理又は同意して行う必要がでてきます。
2 成年後見、保佐、補助の違い
成年後見は、精神上の障害により事理を弁識する能力を「欠く」者とされ、一人ではほぼ判断できないことが前提になっています。
そのため、日用品購入等ごく日常のこと以外は、成年後見人が代理で行います。
保佐は、精神上の障害により事理を弁識する能力が「著しく不十分」である者とされ、訴訟、不動産の売買、借金など重要な行為は、保佐人が代理して行ったり、保佐人が同意
しなけば行えないことになります。
補助は、精神上の障害により事理を弁識する能力が「不十分」である者とされ、代理して行うのではなく、一部の行為に同意を与えたり取り消したりする権限を補助人に与えます。
3 成年後見人等には、ご親族が選ばれる場合と弁護士等の専門家が選ばれる場合がある
成年後見人、保佐人、補助人は、いずれも家庭裁判所に申請して選任してもらいますが、ご親族の方がなるか、弁護士等の専門家がなるかはケースバイケースです。
財産も少なく、ご親族間で誰が成年後見人をやるかで意見が一致している場合等は、配偶者かお子様がなるケースが多いです。
逆に、財産が多かったり、成年後見人をつけるかつけないか等親族間で争いがある場合は、弁護士等の専門家が選ばれがちです。
成年後見人等は、裁判所に財産の管理状況を定期的に報告する等やるべきことも多いので、専門家が成年後見人等に就任するなら、毎月数万円の費用が必要です。
役員全員の同意が得られなくても会社の破産はできる
1 会社の破産は、取締役全員の同意を得て行うのが原則
会社が破産する場合は、会社の取締役会で会社の取締役の決議を行い、全員の同意を得て自己破産の申立てをするのが原則です。
会社の破産は、会社をやめるという大きな判断なので、経営に責任のある取締役たちが話し合って、破産をしようと決めるのを建前としているのです。
実際に取締役会を開いて一堂に会するのは、時間も労力もかかるので、法人の登記に名前がのっている取締役全員に、自己破産に同意する旨の書面を持ちまわるなどして
同意を得ているケースが多いです。
2 役員の一人の資格での破産申立て
しかし、役員の一人が名目だけで連絡先が分からない場合や、役員の一部が反対している場合に絶対に自己破産できないとすると、資金繰りがつかない会社を経営
する方は、ずっと督促を受け続けることになります。債権者も損金処理することができないままになってしまいます。
そこで、破産法では、会社の取締役の一人だけでも自己破産を希望する場合は、会社の破産申立てができるとしています。条文を見てみましょう。
(法人の破産手続開始の申立て)
第十九条 次の各号に掲げる法人については、それぞれ当該各号に定める者は、破産手続開始の申立てをすることができる。
一 一般社団法人又は一般財団法人 理事
3 準自己破産の申立て
これにより、株式会社の取締役だけでなく、一般社団法人や医療法人の理事なども一人で会社の自己破産の申立てができることになります。
実際、取締役同士で対立がある場合等は、対立している取締役に破産することを知らせると、債権者を連れてきて財産が盗まれたるなどの騒動になることもあります。
そこで、他の取締役に知らせずに自己破産申立てするケースもあり、準自己破産と呼ばれています。
ただし、代表取締役が不在の場合等は、特別代理人の選任申立てという手続きも合わせて必要になることがあります。
詳細は会社破産に詳しい弁護士におたずねください。
連帯保証人の債務整理について
1 連帯保証人とは
連帯保証人とは、主債務者(実際お金を借りた人)が約束どおり払わない場合に備えて、一緒に支払義務を負う人です。
法人の借入で法人代表者が、奨学金で奨学生の親が保証人になっているケースが多いです。
2 保証の契約書に記名や押印があれば、基本的に支払義務はある
連帯保証人の方には、主債務者が勝手に保証人欄に書いたから払わないと主張する方もいらっしゃいます。
しかし、基本的に保証の契約書に、保証人の名前が書いてあって、印鑑が押してあれば、保証人自身の意思に基づいて保証したと推定されますので、積極的に別人が全く
保証人の了承なく署名・押印したことを立証できなければ、全額の支払義務を負います。
お金を貸す銀行等の債権者も、保証人の意思確認には注意を払っているので、署名・押印したのが別人でも、別人から保証人に話がいって了承をしている、つまり保証人を代理し
て署名・押印したものと認定されるのが通常でしょう。
そのため、書面があるのに保証契約自体を否定するのは、ほとんどのケースで通用しません。
3 分割払いの話し合いがもっともよくある解決
連帯保証人は、主債務者の支払いが遅れている場合、全額一括で支払わなければなりません。
連帯保証人が債権者と分割払いの話し合いをすることは、通常可能なので、一括払いが難しい場合は分割払いで解決するケースが多いです。
一括で支払う額を減らしてもらうという交渉もありますが、利息や遅延損害金はまけてもらえても、元金が減ることはまれです。
4 法人のの借入の保証人は、経営者保証ガイドラインを検討することも
例外的に大幅に保証債務が減る可能性があるのは、経営者保証に関するガイドラインが成立した場合です。
これは、法人の保証債務しか借金がない場合に、全金融機関の同意が得られれば、保証債務が大きく減ります。
ただ、法人が自己破産等の手続きをしていることが条件になる等、使えないケースもありますので、詳細は弁護士にご確認ください。
5 保証人が個人再生や自己破産することもある
分割で支払うのも難しい場合は、保証人自身が自己破産すれば、保証債務を支払わなくてよくなります。
個人再生という、裁判所に申請して、保証債務を5分の1から10分の1程度に減らして、3年から5年分割で支払う方法もあります。
法人代表者の個人再生
1 法人代表者が個人再生を選ぶメリット
個人再生は、裁判所に申請して借金を減額してもらい、3年から5年で返済する手続きです。
法人の代表者は、法人の資金繰りに困った場合、自己破産したり、分割払いの話し合いをされる方が多いです。
しかし、自己破産の場合は、持ち家を手放さなければなりませんし、法人の役員を一旦退任しなければなりません。
分割払いの話し合いで払っていける負債額ならよいのですが、数千万の負債になると、分割払いで払いきるのは困難になります。
個人再生では、裁判所で借金を5分の1や10分の1に減らしてもらえば、役員をやめることなく、自宅も残して借金の負担を軽くすることができます。
2 法人代表者の個人再生の難しさ
ただ、個人再生は、サラリーマンを主な対象とする手続きであり、法人代表者には独特の難しさがあります。
第1に、法人に対する貸金や出資持分の処理の問題です。
個人再生では、少なくとも持っている財産全額分は、返済しなければなりません。
たとえば、1000万円の負債がある法人代表者が、法人に300万円貸し付けており、法人の株式(出資持分)を100万円有していれば、400万円の財産を持っているこ
とになります。
すると、最低400万円を返済しなければなりません。
第2に、法人代表者の収入の不安定さです。
個人再生は、借金を減らせば安定して返済できることが認められる条件です。
役員報酬が約束どおりもらえて、役員報酬から生活費を引いても余剰が出ていれば、安定して返済できるのですが、実際は役員報酬がもらえていないケースが多々あります。
収入が安定しないと、借金を減らしても返済できないと判断されて、手続きが認められない可能性があります。
3 まとめ
法人代表者の個人再生は、事業を続けながら借金を減額できる有効な手続きですが、経験豊富な弁護士でなければ、返済額がほとんど減らなかったり、手続きが認められない可
能性が十分あります。法人の債務整理や法人代表者の個人再生に詳しい弁護士に十分相談して方針を決めるのがよいでしょう。
中小企業活性化協議会を使った債務整理
1 中小企業活性化協議会(旧中小企業再生支援協議会)とは
先日、企業様が中小企業活性化協議会の窓口相談に行くのに同行してきました。
中小企業活性化協議会とは、国が都道府県ごとに設置した中小企業の資金繰りを支援する機関です。多くの件で商工会議所の中に設置されています。
資金繰りに困っている企業が、自社の課題を客観的に分析したり収益改善のための計画を立てる収益力改善支援、事業計画や金融支援を行う事業再生支援、企業の再生が困難に
なった場合でも代表者や保証人が保証債務の整理を必要になった場合の再チャレンジ支援などの支援事業があります。
弁護士がよく利用するのは、事業再生支援と再チャレンジ支援であり、公正中立な機関として債権者との話し合いの中を取り持ってもらうことがあります。
2 中小企業活性化協議会を通すメリット
⑴ 初回相談は無料
いずれの事業も、初回の窓口相談は無料となっていますので、気軽に相談に行けます。
ただ、1回の相談の機会の実を上げるため、弁護士が同席したり資料を作成する等のお手伝いをすることもあります。
⑵ 債権者との交渉がまとまりやすい
中小企業活性化協議会のスタッフは、金融機関のOB、公認会計士、弁護士などが多いです。金融機関からすると、金融機関の考え方がよく分かっているOBがおり、交渉成立の
実績も多いため、返済額を減らす稟議も通しやすくなります。
⑶ 認定経営革新等支援機関が経営改善計画を策定する場合に一部費用の補助が出る
国が認定する経営改善計画の作成のプロである認定経営革新等支援機関が、このように今後の売上を増やして経費を減らしていくという経営改善計画を作る際に、企業が認定
機関に払う費用が一部公費でまかなわれるメリットがあります。当グループの税理士法人心も認定機関になっています。
3 デメリット
⑴ 本格的な支援には費用がかかる
借金額を減らしてもらう等本格的に支援を受ける場合、中立な立場の公認会計士等の関与がいるのが通常で、専門家に払う費用が高額になりがちです。
⑵ 債権カットでなくリスケジュールで終わることが多い
大幅に元金を減らしてもらう話し合いは、近年成立例も増えているものの、リスケジュールという元金はそのままで毎月の返済額を減らすだけで本当に資金繰りができないの
かが厳しくみられる傾向になります。結果的に元金が減らないままというケースが多くなります。
⑶ あくまで話し合いなので、債権者の金融機関が同意しなければ不成立で終了することになります。
4 このようにデメリットもありますが、話し合いで企業の金融機関からの借入の元金を大きく減らすには、最も実績がある機関になります。
小規模な企業でも成立例があるので、事業の再生の相談を受ける弁護士としては、まず初回相談の同行をお勧めするケースも多いです。
不動産の任意売却と弁護士の関与
1 債務整理と不動産の任意売却のすすめ
債務整理をする中で、不動産を売却する機会がよくあります。
自己破産するなら、基本的に破産する方名義の不動産は手放さなければならないですし、不動産を売ったお金を債務整理の返済原資にすることもあります。
債務整理をする中で不動産を売却する場合、任意売却と競売(けいばい)の2つの方法があります。
競売は、住宅ローン債権者などが裁判所に申し立てて強制的に不動産を売る手続きです。
債務整理する方は、競売であれば裁判所の職員等が建物内を見に来るときに立ち会うこと、売却終了までに引っ越すことだけすればよいので、手間は少ないです。
ただ、任意売却という自身で不動産業者を通じて売りに出した方がよいケースが多くあります。
2 任意売却が競売よりメリットがあるケース
一つは、不動産を売れば住宅ローンが完済できる可能性がある場合です。少しでも高く売れれば手元にお金が入ってきますので、債務整理の返済原資や弁護士費用に充
てたり、不足している生活費にあてるなど有効活用できます。
競売になれば、競売の費用(最低70万円程度)を負担しなければならず、手元に残るお金が減ります。
二つ目は、近隣住民に知られたくない場合です。
競売は、インターネットに情報がのるので、誰でもどの不動産が競売されているか見ることができます。これを見た不動産業者が自宅を訪ねてくることも多いです。
任意売却であれば、普通に引越しして自宅を買い替える人と同じように売買するので、近隣住民に債務整理していることを知られずに済みます。
三つ目は、スケジュールを調整したい場合です。競売は、債権者が申し立てるので、スケジュールを調整することは困難です。任意売却なら、自身で売りに出すので、引越のタイ
ミング等をある程度調整できるのです。
3 任意売却に弁護士が関与するメリット
任意売却は、ご自身で不動産業者を選んで最後まで進めることもできます。
ただ、債務整理の一環で任意売却する場合は、2つの理由から、弁護士が関与する方がよいです。
一つは、債権者や裁判所は、不動産をなぜその金額でその相手に売ったのか説明を求めてきます。売買の過程から債権者に説明する弁護士が関与すれば、債権者への説明も適切
になり、債権者との交渉の成果も上がりやすくなります。
二つ目は、不動産を売ってもローンが残るケースでは、弁護士が入るか任意売却に特化している不動産業者が交渉するのでなければ、そもそも不動産が売れません。
住宅ローン債権者にローンが残るのに担保を外してもらうには、独特の交渉が必要になりますから、不動産業者選びの段階から弁護士と不動産業者が連携する方が成果が出ます。
司法修習生の研修講師
1 司法修習生とは
先日、愛知県弁護士会という私も所属する弁護士の業会団体で、司法修習生向けの倒産実務研修の講師を務めました。
司法修習生は、司法試験に合格して、裁判官、検察官、弁護士になるための研修を受けている方です。
裁判所、検察庁、法律事務所(弁護士)に行って研修を受けるほか、弁護士会が主催する研修を受講することもあります。
私が講師を務めたのは、倒産実務委員会が行っている、破産や個人再生の事例をもとに少人数で議論をするバズセッションです。
2 弁護士になる前に倒産案件を学ぶ機会がない司法修習生も多い
弁護士になると、債務整理は法律相談でよく見かける案件です。
ただ、弁護士になる前は、債務整理などの倒産案件を学ぶ機会は意外と少ないです。
司法試験には、選択科目の中に倒産法(主に破産法と民事再生法)がありますが、必修科目ではないので、選んでいない人の方が多いです。
また、司法試験を受験する前の大学や法科大学院には、倒産法の授業が選択できたでしょうが、選択していない人も多いです。
3 自己破産の事例
従業員が1人いる個人事業主が自己破産する場合に、どの程度の期間がかかるか、裁判所に行く必要があるか、弁護士費用と裁判所に納める予納金をどうやって準備するかなど議
論しました。
従業員の給料が払えない場合は、労働者健康安全機構の未払賃金立替払制度が使えることなど、実務に直結する内容になっていました。
4 個人再生の事例
住宅ローンのある自宅を残したいサラリーマンが、個人再生する場合にいくら返済すればよいか、家計の状況をもとにどのように支出を減らして返済可能な状態にもっていくか
など議論しました。
住宅を残す個人再生では、住宅ローンはそのまま払い続けるので減額されず、他の借金が減額されるのですが、住宅ローンも減額の対象になるという司法修習生の回答が散見さ
れたのが印象的でした。
5 司法修習生を相手に話すことは、改めて私の弁護士としての仕事のスタンスが正しいかや、実務でよく行われていることの法律上の根拠を再確認する意味でも有意義でした。