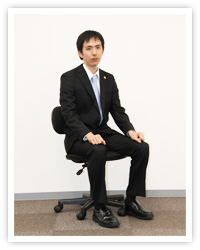個人再生では,収入から生活費を支払っても余りがあって,余りで返済の見込みがあると裁判所が認める必要があります。
借金の相談に来られる多くの方がギリギリの生活をされているので,この要件を満たすか微妙な方は少なくありません。
1 認められない例:専業主婦,無職で失業保険しか収入がない
まず認められないことがほぼ確定している例をお話しします。
専業主婦の方は,配偶者の収入から返済できるとしても,ご自身は収入を得る見込みがないとして,個人再生は認められません。
また,無職の方は,年金で固定収入がある方はよいのですが,そうでない方は,認められません。
失業保険や傷病手当は,いずれもらえなくなることが決まっていますので,次の就職先が決まってその収入から返済できることが示せなければ,個人再生の
最低返済期間である3年間,収入が続くとはいえないからです。
2 派遣社員は認められることが多いが,無収入の期間が多いと問題がある
派遣社員の方は,労働者派遣法の関係で3年を超えて同じ部署に派遣されないことや,派遣先の状況で無収入になることがある点で,正社員の方より難しいケースがあります。
それでも,一定期間収入がある状態が続いていれば,個人再生が認められることが多いです。
問題があるのは,派遣先が見つからず無収入の期間や,数万円の収入しかなく生活費の方が多い月がたびたびある場合です。
この場合は,現在の派遣先に行ってからの期間や,過去の就業実績をもとに,個人再生の返済期間である3~5年間,その収入が得られる可能性が高いとどこまで証拠が出せる
かによります。
3 契約社員は認められることが多いが,契約更新の実績による
契約社員の方は,契約が更新されなければ無収入になることがある点で,正社員の方より難しいケースがあります。
こちらは,契約期間が決まっている分,契約更新の確率が最も重要です。
過去に複数回更新実績があればよいですが,ない場合は,他の同様の待遇の方が更新されているかや,過去の就業状況をもとに,個人再生の返済期間である3~5年間,その収
入が得られる可能性が高いと認められるかが問題になります。
転職歴が多い方は,転職の理由から今回の仕事が続きそうかどうかがみられたり,職の間に無収入の期間がないかどうか等も問われます。
4 弁護士への積立の実績も重要
個人再生では,弁護士に依頼した後は,債権者への返済をやめ,代わりに弁護士の事務所の口座に毎月数万円ずつ積み立てるのが通常です。
この積立額の実績が,将来返済に回すことができる額とみなされるので,積立てが途切れないことも個人再生が認められる重要な要素です。
個人再生で返済の見込みがあると認められるか微妙な方は大勢いらっしゃいますが,積立ての実績を作り,生活費の節約も合わせて行い,収入がある状態が続いていれば,認められる例が多いでしょう。
個人再生できるか不明な方も,相談自体は無料ですので,お気軽に弁護士までお問い合わせください。