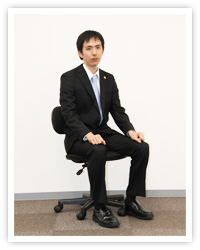日々思ったこと、皆様のお役にたてる情報などを書いていきたいと思います。
ようこそ、弁護士 岩橋 毅彦のブログへ
個人破産と異なる法人破産の注意点
会社(法人)の破産には、個人の破産にはない独特の注意点があります。法人の破産では、必ず管財人という裁判所が第三者的な立場の弁護士を選び、問題ないかをチェックする制度になっています。ここでは、管財人の経験もある弁護士として、個人破産と違って法人破産特有の注意点をお伝えします。
1 法人と代表者の個人のお金の行き来
法人と代表者個人は、法律上は別人格なので、法人の資産は法人の資産、代表者の資産は代表者の資産で区別して管理するのが建前です。
ただ、破産する会社では、法人と代表者や役員の間で不適切にお金が流れており、ごちゃまぜになっていることが多いです。
特に、代表者が、法人のお金を理由もなく私用に使ったり隠し持つことは、法人の債権者である下請や仕入先からすると、横領や背任の疑いがある行為ということになります。
そこで、法人から代表者にお金が不適切に流れていないか、たとえば法人の売上を代表者個人の口座に振り込ませたり、法人のお金で代表者個人の借金を返済したりしていないか
チェックすることになります。
2 法人の廃業直前から廃業後のお金の流れ
法人にはたくさんのお金の流れがありますが、破産手続で注意すべきなのは、通常の取引と違うイレギュラーなお金の流れです。
たとえば、車を売却するとか、個人の債権者にまとまって返済する等は、通常の会社の取引ではないので、管財人は、どういう意図で行い、適切なお金の流れなのか検証します。
特に廃業直前や廃業後は、もう法人が破産する予定であった可能性が多分にあるので、どうせとられるなら代表者が自分で使い果たしたり、親しい人にだけ良い思いをしてもらお
うと不適切なお金の流れをしがちですので、管財人のチェックも厳しくなります。
3 法人の契約は全て解除し、財産は全てお金にかえなければならない
個人の場合は、自己破産しても今後も生活していくので、自宅の賃貸借契約や水道光熱費等の契約はそのまま残るのが原則ですし、最低限の預金や掛け捨ての保険も基本的に残せ
ます。
しかし、法人は法人格自体がなくなるので、賃貸借であれ携帯電話であれば契約は解除し、ほぼ価値のない車や預金も売却や解約で現金化しなければなりませんので、管財人は法
人の契約や財産が残っていないかをチェックすることになります。
破産管財人の否認権行使への対応
1 破産管財人の否認権行使とは
破産管財人は、自己破産の申立てで、ある程度財産がある場合や、借金が増えた経緯に問題がある場合に、裁判所が調査のために選任する弁護士です。
破産管財人は、破産前に問題のあるお金の使い道があれば、取り返してきて債権者に配る財産を増やすのも仕事です。
たとえば、破産者Aが、弁護士に破産を依頼した後に、母Bから借りていた20万円だけ返済してしまったとします。
破産管財人は、他の債権者は返してもらっていないのにBだけ20万円返してもらったのは不平等であるとして、Bに対し、20万円管財人に払うよう請求できます。
管財人は、Bから20万円取り返して、他の債権者にも分配します。これを、AのBに対する返済の効果を否定することから、破産管財人の否認権の行使といいます。
2 Bに理解を得られるよう説明する
ここでは、破産を依頼される方Aの立場にたって、どういう対応が考えられるか検討します。
母Bからしても、約束どおりAに返してもらっただけなのに破産管財人なる弁護士から請求されるのは、驚かれると思います。
ただ、Bが20万円を返してくれないとなると、場合によってはAが免責不許可(借金がチャラにならない)になったり、管財人がBに裁判を起こすかもしれません。
Bにより迷惑がかかるので、AからもBに説明して、20万円を管財人に払うよう説得することが考えられます。
3 破産者や第三者が破産財団に組み入れる
それでもBが20万円を払えないときには、A自身が収入や財産から20万円を払うことも考えられます。
また、ご兄弟等第三者に援助してもらって20万円を用意することも考えられます。管財人としては、20万円Bに払っていなければAの財産として残っていたは
ずの20万円を、他の債権者に配れればよいので、誰が20万円を用意しても柔軟に対応することが多いからです。
4 破産管財人の否認権行使は、依頼する弁護士に相談せずに勝手に返済してしたり、財産を渡したことが原因で問題が生じるケースも多いです。
勝手に返済したり財産を渡す前に、依頼する弁護士によく相談しましょう。
経営者保証ガイドラインと特定調停
1 特定調停とは
返済が困難になりそうな個人の方が、簡易裁判所に申し立てて、裁判所が選ぶ調停委員等に仲介してもらい各債権者(消費者金融、銀行、カード会社等)と話し合いで借金の整理をする手続きです。
過払い金が多く発生していた頃は、弁護士に依頼せずご自身で申し立てて借金の整理をする方もいましたが、現在は過払い金がほとんど発生せず、任意整理(裁判所を通さず各債権者と話し合いをする)に比べてデメリットが大きいでしょう。
たとえば、裁判所で手続きするので手間がかかりますし、払えなければすぐに差押えされる状態になります。
債権者間の平等が原則なので、最も短い返済期間しか認めないところに合わせなければならなくなりがちです。
このため、消費者金融やカード会社相手にやるケースはほとんどなくなっています。
ただ、平成26年以降、経営者保証ガイドラインができてからは、会社代表者など、会社の借入の保証人になっている方の借金の整理の方法として注目を集めています。
2 経営者保証ガイドラインでは特定調停の申立てが推奨されている
経営者保証ガイドラインは、会社の借入の保証人になっている方(会社代表者や取締役等)が、会社が破産や民事再生したときに一括請求を受ける保証債務について、各債権者
(信用保証協会や銀行等)と話し合いをして、借金の元本を減らしてもらうものです。
通常の話し合いでは元本を減らしてもらうのは困難ですが、経営者保証ガイドラインを使うと、大幅に元金を減らすことができます。
ただ、債権者は税務上損金処理ができないと困るので、特定調停で裁判所のお墨付きを得ることが必要になるのです。
3 特定調停の進め方
弁護士を通して経営者保証ガイドラインの話し合いを各債権者の担当レベルではOKをもらっておきます。
弁護士が簡易裁判所に特定調停の申立てをして、裁判所に経営者保証ガイドラインの要件を満たすこと等を確認してもらい、第1回目の裁判期日で調停が成立するのが順調な流れ
です。
ご本人は裁判所に出頭する必要がないのが通常ですので、会社代表者で保証債務以外にほぼ借金がないという方は、検討してみるとよいでしょう。
会社の破産と従業員の関係
1 会社の破産で従業員は解雇になる
会社が破産する場合、従業員は基本的にやる仕事がなくなりますし、給料が払えないケースも多いので、破産することを公にした時点で解雇されるのが原則です。
従業員は、給料ももらえず生活に困る方が出てきますので、会社が破産する場合でも以下のような手続きをできるだけ速やかに進める必要があります。
2 給料の未払いは未払賃金立替払い制度を検討する
給料が払えないで破産する場合は、独立行政法人労働者健康福祉機構の未払賃金立替払制度の利用を検討します。
給料の80%までを立て替えて払ってもらえる制度ですが、様々な資料を揃えて破産管財人が証明して申請しなければならず、未払になってから実際にもらえるまでは半年近くか
かることも多いです。
詳細は、以下の機構のホームページをご参照ください。https://www.johas.go.jp/chinginengo/miharai/tabid/417/Default.aspx
3 失業保険の手続き
雇用保険に加入している従業員は、失業保険を受給することができます。
これには、会社が離職票を準備してハローワークに提出する必要がありますので、社会保険労務士に依頼するか代表者ご自身で作成して提出するのが通常です。
4 社会保険の資格喪失と国民健康保険等への切替
会社の社会保険に加入していた従業員は、会社が社会保険の資格を喪失させて、国民健康保険や次の勤務先の社会保険等にうつらないと無保険状態になってしまいます。
従業員が病院に行く際に健康保険が使えないと生活はより苦しくなりますので、社会保険労務士に依頼するか、代表者ご自身で速やかに年金事務所等で社会保険の喪失手続きをす
る必要があります。
5 会社破産に詳しい弁護士と段取りを相談
従業員関係の手続きは、会社破産の中でも重要な位置を占め、急ぎでやらなければならないことが多いです。段取りは、会社代表者と会社破産に詳しい弁護士でよく打ち合わせるようにしましょう。
重要判例解説令和6年版
毎年有斐閣から重要判例解説という、去年1年間に出た実務上意義の大きい裁判例をまとめた書籍が出版される。弁護士の必読書の1つといえる。
その中から、私が注目したものを一つ紹介する。大阪高裁令和5年12月19日判決(令和5年(ネ)62号)である。
1 事案の概要
Xは、協同組合Yの組合員であり、501万円の出資を行っていた。Xは通常民事再生を申し立てて令和2年1月開始決定を得て、令和3年3月末のYの事業年度末でYを脱退して出資金を払い戻す意思表示をした。YはXに対して約1000万円の貸金債権を有しており、令和3年2月に1000万円の貸金債権の債権届出をするとともに、出資金払戻債務を対当額で相殺する意思表示をしたが、XはYに対し501万円の支払を求めて提訴した。
出資金は、前年9月までに脱退の申込があれば、翌年6月の総代会で払戻金額を確定して総代会終了後に払戻しを行うので、Yの相殺は停止条件不成就の利益を放棄して行われた。
2 判決の要旨
民事再生法92条1項は、再生債権者が相殺によって消滅させることのできる債務の範囲を制限することで、再生債権者の相殺の担保的機能への期待と再生債務者の事業の再建との調整を図ったものである。
同項により再生債権者がすることが許される相殺における受働債権にかかる債務は、再生手続開始当時少なくとも現実化しているものである必要があり、将来の債務など当該時点で発生が未確定な債務は、特段の定めがない限り含まれないと解するのが相当である。
このことは、旧商法上の会社整理で停止条件付債務を内容とする契約が会社の整理開始前に締結された場合であっても条件が整理開始後に成就したときは相殺を禁止していると解されていたこと(最判昭和47年7月13日)にも整合する。
として、Yの相殺の主張を認めず、Xの出資金払戻請求を認容した。
(参考:民事再生法92条1項:再生債権者が再生手続開始当時再生債務者に対して債務を負担する場合において、債権及び債務の双方が第94条第1項に規定する債権届出期間の満了前に相殺に適するようになったときは、再生債権者は、当該債権届出期間内に限り、再生計画の定めるところによらないで相殺することができる。)
会社の破産と代表者のその後の仕事
1 会社が破産しても、代表者が仕事をすることはできる
会社が破産・倒産する場合、その会社では破産後に仕事をすることはできません
ん。そのためか、会社破産を弁護士に相談に来られる会社代表者の中には、代表者自身も仕事をしてはいけないとお考えの方もいらっしゃいます。
破産した会社の代表者であったというだけで仕事ができないわけではありません。今後の生活もあるので、就職して収入を得ることは何ら悪いことではありません。
ただ、全く制約がないといえば嘘になるので、破産する会社の代表者が、いつからどのような仕事をするのがよいかお伝えします。
2 会社の保証債務がない場合は制約はほぼない
会社が破産する場合、代表者は会社の借入の連帯保証人になっているのが通常です。
保証債務がない場合は、代表者自身は何の債務整理もしないのが通常なので、代表者が仕事をするのは、業法で破産した会社の代表者であった場合につけないもの以外に法的な制約はないといえます。
ただ、会社の破産管財人から会社の残務処理に協力を求められた場合に協力したり、会社の債権者集会という裁判所に出廷する機会があるので、平日の昼間に数回仕事を休んででも協力する必要があります。
3 代表者も自己破産する場合は、役員に就任したり資格の制限に注意
会社の多額の保証債務を負っている代表者は、自身も自己破産することが多いです。
この場合、別の会社の役員に就任していても、退任しなければなりませんし、警備員・保険外交員・古物商等に破産法の資格の制限があるので、就く仕事に注意が必要です。
4 個人事業をする場合は、会社の財産を使わず、後払いをしないのが原則
就職はすぐにしても問題ないですが、個人事業の場合はやり方に注意が必要です。
まず、破産する会社の財産(機械、事業所、車等)を使って事業をするのは基本的に認められません。破産する会社の財産は全て破産管財人が売却しなければならず、会社から個
人に無償で引き継ぐことは財産隠しになります。管財人がついてから会社の財産を代表者が適切な値段で買い取って使用するなら、管財人がつくのを待つことになります。
また、従業員を雇ったり後払いの仕入や外注を使うと、売上が思ったタイミングで入らなかったときに個人で負債を負う可能性があります。
代表者が破産するのに負債を新たに負うのは問題があるので、一人親方等負債を負わない形態にする必要があります。
5 代表者が次の仕事に就くことは基本的に望ましいですが、やり方や時期は考える必要がありますので、詳細は弁護士までおたずねください。
浪費がある場合の同時廃止か管財事件か区別
1 自己破産には、同時廃止と管財事件の2種類がある
自己破産は、裁判所に申請して借金を0にしてもらう手続きです。
自己破産には、同時廃止と管財事件と2種類あります。
同時廃止は裁判所に納める費用が約1万5000円ですみ、裁判所に行かないでよいケースが多いですが、管財事件は裁判所に納める費用が最低20万円以上かかり、裁判所に原則行かなければなりません。
自己破産を依頼する方は、管財事件でなく同時廃止になる方がメリットが大きいでしょう。
ただ、浪費が多いと免責観察といって、借金を0にしてよいかどうか裁判所が選
ぶ管財人という弁護士の指導・監督が必要という理由で管財事件になります。
ここでは、パチンコや競馬、服の買いすぎ、投資の失敗等の浪費がどの程度で管財事件になるかという感覚をお伝えします。
2 浪費の時期と金額
まず、浪費の時期が自己破産の申請に近く、金額が多いほど管財事件になります。
たとえば弁護士に自己破産を依頼した後にギャンブルをした場合は、依頼後の総
額が20万円程度でも管財事件になるのが通常です。
弁護士に依頼する直前までギャンブルしていたが、依頼後はやめているケースで
は、月に5万円程度までなら同時廃止になりやすいでしょう。
借金が払えなくなる2,3年前にはやめているなら、月10万円弱のギャンブ
ルがあっても、同時廃止になりやすいと思います。
3 浪費以外に借金が増えて払えなくなった原因を説明できるか
浪費した額以外に、やむをえない出費が増えたとか、収入が下がったなど、それ
まで返済できたのに事後的に生じた原因で払えなくなったと説明できるかがポイント
になります。
たとえば、同じ月額5万円のギャンブルがあったとして、子どもの大学進学で想定以上に教育費が増えたなら、払えなくなったのはギャンブルでなく子供の進学であるとして、同時廃止になりやすいでしょう。
4 債務総額
自己破産で免責(払わなくてよくなること)してもらう債務額もポイントになり
ます。
子供の奨学金や住宅ローンのような使い道が明確なもの以外に、500万円以上借金があると管財事件になりやすいといわれています。
5 このように、同時廃止か管財事件かは、様々な事情を考慮して裁判所が決めますが、弁護士に見通しを聞く場合は、自己破産の経験豊富な弁護士に聞くことをお勧めします。
会社代表者の手続費用を会社の財産から準備することについて
1 会社代表者の費用と会社の費用を両方用意しなければならない
会社が支払いができずに倒産する場合、弁護士に依頼して会社の自己破産をするのが通常です。
会社が支払いができないと、連帯保証人である代表者に対して一括請求されますので、会社代表者も自己破産しなければならないケースが多いです。
会社と会社代表者が両方破産するとしても、別人格なので、会社の破産費用と会社代表者の破産費用の両方を準備しなければなりません。
2 会社代表者の費用は代表者の財産から、会社の費用は会社の財産から用意するのが建前
会社の財産と会社代表者の財産は、破産手続では明確に区別されます。会社代表者の破産費用は、代表者自身の財産や収入からまかなうか、ご親族等に援助してもらうのが王道で
す。
会社の売上から会社の破産の費用をまかなうのはよいですが、会社の売上から会社代表者の破産費用までまかなうのは、建前上は会社の財産を代表者が横領したとか背任であると
いわれる可能性もあります。
3 会社代表者の費用も会社の財産からまかなうことが許容される場合もある
会社代表者がギリギリまで会社の事業を続けようとして個人資産がなくなるまで会社に投じてしまったときに、会社は破産できても会社代表者が費用がなくて自己破産できなけれ
ば、代表者は経済的にやり直す機会がなくなってしまいます。
これはあまりに酷なので、会社代表者が自身の財産で費用を準備できない場合には、会社の売上等の財産から代表者の破産費用を出すことが許容されるケースも多いです。
たとえば、会社代表者が会社に対して貸付を行っていた場合は、貸付金を回収して破産費用を捻出する等の説明をすることがあります。
会社代表者が役員報酬を長らくもらっていなかった場合は、役員報酬として破産に必要な費用を会社から受け取ったという説明も考えられるところです。
このように、会社代表者に資産がなくても、会社の財産や売上から破産費用を捻出できてやり直せるケースもありますので、詳細は弁護士までおたずねください。
住宅ローンが払えないときの対応
1 住宅ローン会社で支払額を見直す
収入が減って住宅ローンが払えなくなる方の相談はよくあります。住宅ローン以外にほとんど借金がない方の場合、最初に考えるのは住宅ローン会社に相談することです。
借り換えで返済期間が長くならないかや、ボーナス払いをならしたり、返済期間を延ばすことで、支払額が減って資金繰りがつくケースもあります。
2 住宅ローン以外の借金の任意整理やおまとめローン
住宅ローン以外や車のローン以外の借金が数百万円あるなら、住宅ローン以外の借金の返済額を減らす方が効果的なことが多いです。
住宅ローン以外の借金は、利率も高く、借入額の割には返済額が大きく設定されていることが多いからです。
おまとめローンが組めて、返済先が一本化できて、金利も下がり、返済額も減るなら一つの解決になります。
ただ、おまとめローンで一部しかまとめられないケースや、返済額が減らないケースも多いです。
任意整理という、弁護士等の専門家を通した分割払いの話し合いなら、金利を0に近づけて毎月の返済額もおおむね5年(60回)払い程度まで減ることが多いです。
3 個人再生
住宅ローン以外の借金がかなり多くなると、分割払いの話し合いでは支払いきれなくなり、個人再生という裁判所でやる手続きを検討します。
住宅ローンは約束どおり支払い続けて自宅を残し、それ以外の借金はおおむね5分の1まで減るので、住宅ローン以外の借金の負担は大きく軽減されます。
4 不動産の任意売却やリースバック
住宅ローン以外の借金が少なく、自宅を手放してもよいと思える場合は、自宅を任意売却するのがよいでしょう。
住宅ローンを完済できないと売れないという不動産業者等もいますが、実際は住宅ローンの会社が担保を外してくれれば売れるので、住宅ローンの残額を下回っても売れる場合が
あります。
また、自宅に住み続けたいが自宅の所有にこだわらない方なら、リースバックという、自宅を不動産業者に売って一時的に現金を得て、賃料を払って住み続けるケースもありま す。
5 自己破産
どうやっても住宅ローンが払えない場合や、離婚等で持ち家を維持するメリットがなくなっている場合は、自己破産するのが最も楽になる方法です。
自宅は手放すことになりますが、借金はゼロになって、収入があれば少しずつ貯金できるようになるでしょう。
相続財産清算人の選任申立てとは
1 相続財産清算人は相続人がいないケースで選任される
相続放棄した方から、相続財産清算人の選任申立ての相談を受けることがあります。
以前は、相続財産管理人といわれていましたが、令和5年4月1日の民法改正以降は、相続財産清算人といいます(令和5年4月以降も相続財産管理人という制度はあるのです
が、権限が縮小されて使うケースは少なくなっています)。
相続財産清算人は、相続人がいないケースで、相続財産を利用したい人や相続の対象となるはずの負債を払ってほしい人が裁判所に申請することで選任されます。
ほとんどのケースで、亡くなった方の住所地を管轄する地域の弁護士が選ばれます。
2 相続放棄した人が管理責任を免れたいとき
亡くなった方の子どもや兄弟など相続人となる可能性がある人全員が相続放棄をしても、たとえば相続財産である不動産に居住したり物を保管している場合
は、管理責任がありますので、不動産が崩れて通行人がケガをした場合等に損害賠償請求を受ける可能性があります。
これを免れるためには、全員の相続放棄が終わった後に相続財産清算人の選任申立てをします。相続財産清算人から自宅だけ買えば、相続財産である自宅に住み続けることがで
きるわけです。
3 債権者が相続財産から支払いを求めたいとき
亡くなった方が税金を滞納しており、不動産や保険など財産がある場合、税務当局は不動産や保険をお金にかえて税金を取り立てる必要があります。
このとき、税務当局が相続財産清算人の選任申立てをします。
4 特別縁故者が財産分与を得たいとき
亡くなった方の介護を長年したが血がつながっていない場合に、特別縁故者として相続財産から支払いを受けられるケースがあります。
特別縁故者となる予定の方が相続財産清算人の選任申立てをします。
5 費用やスケジュールなど
相続財産清算人の選任申立ては、一般の方なら弁護士を依頼するケースが多いでしょう。弁護士の費用のほか、裁判所に支払う予納金が相続財産清算人の報酬を確保するために
必要で、現金化しやすい預貯金等が多ければ0円のケースもありますが、一般には70万円~100万円など相当額が必要です。
ただし、相続財産が現金化できたときには返ってくるケースもあります。
相続財産が全てお金にかわって債権者の皆さんに平等に配られるまで続くので、不動産が複数ある方などは1年以上かかるケースもあります。