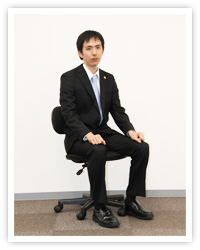破産の債権者集会のため、岐阜地裁御嵩支部に行ってきました。
個人の方の破産では、裁判官が債権者集会で積極的に質問するのは珍しいですが、今日は裁判官自ら20分以上質問されていました。
帰りはのんびり周囲を観光してきました。
岐阜地裁御嵩支部
過払金返還請求のセミナー
「過払金返還請求の最新動向」というテーマで,証券会社の方向けのセミナーの講師をしました。
過払金返還請求は,ここ3年間程度でも少しずつ件数も金額も減っているものの,平成27年から平成28年にかけては,ほとんど変わらず推移しています。
大手貸金業者の中にも,新たに利息返還引当金を積み増している業者もいます。
平成22年以降に新たに契約した取引は,過払金が発生しないため,理論上は徐々に減っていくはずですが,急激に減ることはないと思われます。
そんな中,一部の業者が,過払金の返還時期を遅くするために訴訟を長引かせたり,少額の返還にこだわる傾向は,少しずつ強くなっているように感じます。
依頼者さんの要望に沿いつつ,徹底的に過払金の回収率を高める姿勢が弁護士に求められています。
刑事事件の判決言渡し
今日は,私が弁護人をしている刑事事件の判決の言い渡しがありました。
民事事件では,判決文は事務所に送付されるので,判決の期日には出席しないことの方が多いです。
一方,刑事事件の第一審の判決の言渡しは,弁護人は原則として立ち会わなければなりません。
判決文は,あえて交付申請等をしない限り送付されず,判決の結果や判決理由によって控訴するか検討しなければなりません。
公訴事実を認めている場合は,言渡しは5分程度で終わりますが,理由が分からなくならないよう,しっかりと記録しておく必要があります。
破産手続と養育費の扱い
養育費を支払う側が自己破産する場合,養育費を支払うべきか悩ましい場合があります。
まず,破産手続開始決定後に発生する養育費は,金額が不相当に高額でない限り,支払うことに問題はないと考えられています。
一方,破産手続開始決定前に発生した養育費を滞納している場合,養育費の支払義務は破産債権として,他の消費者金融や銀行からの借入と平等に取り扱わなければならず,破産手続中に支払うのは適切でないのが原則です。
しかし,破産手続開始決定前の養育費は,自己破産して免責決定を得たからといって,支払義務を免れる訳ではありません。
そうすると,破産手続開始決定前の養育費は,破産手続が終わった後に,分割等で支払わなければならないことになります。
弁護士に自己破産を依頼してから破産手続開始決定を得るまでの間の支払も,毎月発生する分を約束どおり払う場合は,金額が不相当に高額でない限り問題ありませんが,過去に滞納した養育費を上乗せして払う場合は,一部の債権者を優遇したとして破産手続で問題となると考えられます。
管財人は敵か
破産の申立てをして管財人がついたとき,依頼者さんから,管財人がどういう立場なのか質問を受けることがよくあります。
管財人は,破産法の建前上は,公平中立な第三者的立場です。
管財人は,裁判所が選び,債務者(破産する依頼者さん)と債権者(お金を貸した業者等)の利害を調整して適切に財産を分配し,財産を分配しても残っている借金を免除してよいか(「免責」といいます。)どうかに関しても意見を述べます。
ただ,依頼した弁護士は,依頼者さんの味方で,原則として依頼者さんの利益を代弁しますが,債権者の利益を代弁する人は,管財人以外にいないこともあるので,依頼者さんからすると,管財人は対立相手のように感じることもあるでしょう。
その考え方は,必ずしも間違いとはいえませんが,多くの場合,管財人は,正直に資料を提出して破産手続に協力した破産者には,免責しよう,借金をなくして立ち直りの機会を与えようと考えているものです。
破産する方が管財人に求められた資料を提出したり説明するのは,破産法の定める義務ですし,特に浪費が問題になっている場合等は,管財人の指示に従って協力することが,借金をなくして立ち直るために役立つことが多いです。
とはいえ,財産を残すことを希望しているが管財人が認めない場合や,一部の債権者にだけ返した行為が問題になっている場合は,管財人と違う見解を持つこともあるので,依頼した弁護士に気軽にご相談ください。
破産管財人の立ち位置
自己破産で財産が一定額以上あるときや債務が増えた経緯が良くない場合,破産管財人が裁判所から選ばれる管財事件になることがあります。
裁判所が,案件ごとに弁護士に対して管財人への就任を打診し,弁護士が裁判所にある記録を見に行って,その案件の管財人を引き受けるかどうか決めます。
裁判所は,弁護士ごとに管財人になった際の事件処理の仕方を管理しており,事件の難易度に応じて就任を打診する弁護士を決めていると言われています。
そこで,管財人になる弁護士は,次の管財事件でも裁判所に選んでもらえるよう,裁判所の意向に沿って活動する傾向が見られます。
私も管財人を引き受ける際は,裁判所と相談しながら事件を進めます。
逆に,私が依頼者さんを代理して破産の申立てをする側の場合,管財人の弁護士を味方につければうまく裁判所を説得してくれるケースもありますし,管財人の考え方が依頼者さんと食い違って対立するケースもあります。
管財人との関係の持ち方は,案件の解決に大きな差をもたらすこともあるので,過去の経験も踏まえて慎重に対応するようにしています。
債務整理における業務範囲
司法書士が債務整理に関して取り扱うことができる業務範囲に関する最高裁判所の判決が,平成28年6月27日に出ました。
一般に,弁護士は,取り扱うことができる額に制限はありませんが,司法書士は,紛争の目的となる価額が140万円を超える事件の代理はできないとされています。
訴訟によらずに分割払いの交渉を行う任意整理の場合,この140万円をどうやって算定するかが争いになりました。
判決は,各債権の額が140万円を超える場合に代理できないとしています。
単純にいうと,アコムから150万円,アイフルから50万円を借りている方の任意整理の場合,アコムについては司法書士は代理できず,アイフルについては代理できるという趣旨であると理解できます。
なお,自己破産や個人再生の場合,債務額にかかわらず,司法書士は,代理人として活動することができません。
子どもの人権相談
私が所属している愛知県弁護士会の子どもの権利委員会では,子どもの人権相談という法律相談を無料で行っています。
今日は,その担当日でした。
土日に,面談だけでなく,電話相談も受け付け,子ども自身からの相談では,必ずしも名前を名乗る必要もないとされています。
いじめ,虐待,離婚問題,学校の先生や他の子とのトラブル等,幅広い相談を受け付けています。
個人再生申立マニュアルの改訂内容1
個人再生申立マニュアルのうち,私が主に担当した部分は,再生計画案を提出する際の書式集と解説文の整備です。
たとえば,個人再生手続中に住宅ローンを約定どおり払い続けるには裁判所の許可がいりますが,複数の住宅ローン債権者がいる場合の書式を新設しました。
また,もともと日本弁護士連合会が作成した書式は,どんな条項にも対応できる反面,実務でよく使う項目が省略されている等使いにくいところも多かったので,私が事務所で普段用いている条項を採用していただく等しました。
再生計画案は,難解な専門用語を用いる必要があり,内容も複雑ですので,内容の詳細は弁護士までお尋ねください。
個人再生申立マニュアル改訂版
個人再生申立マニュアルという,愛知県弁護士会倒産実務委員会が作成している書籍が,平成28年3月,改訂になりました。
私も改訂作業に携わり,執筆者に名を連ねさせていただきました。
他の民事再生に精通している弁護士や裁判官との議論を通じて,私自身の個人再生に関する考え方をブラッシュアップすることができました。